

貨幣の歴史

貨幣の歴史は日本では西暦683年。
海外でもっとも古い貨幣は諸説ありますが、紀元前4300年頃のアッカドからバビロン第1王朝にかけて「ハル(har)と呼ばれたリング(銀貨)」をはじめ、紀元前から複数の貨幣が流通していたと言われています。
貨幣の歴史と、時代を感じられる人気の古銭を紹介いたします。
物品貨幣から貨幣への変化

貨幣のない時代は、物品による交換で物を買う方法をとっていました。
たとえば猟師が肉を調達したら、その肉を使って猟師から魚を買ったり、職人や商人から衣服を買ったりする物々交換の流れです。
海外をはじめ、紀元前に流通していた貨幣は現在のような成形して特定のデザインを彫ったものではなく、金や銀など希少性の高い素材そのものをお金として使っていました。
その後は重量を設定して貨幣一枚あたりの価値を統一し、特定のデザインで発行する現代の貨幣へと変わっていました。
ただし、古代は現在のように働いて給料を得るシステムではなかったため、貨幣と物品貨幣を併用していて、国が一定のエリアを支配する文化が根付くにつれて、国民共通の貨幣が広く普及していった歴史を持ちます。
日本の貨幣の歴史

日本における貨幣の歴史と主要な古銭の歴史を時系列にまとめました。
有名な古銭は現在の価値も参考情報として紹介しています。
683年
日本最古の貨幣「富本銭」が7世紀後半の飛鳥時代に鋳造されました。
和同開珎よりも古く、発行時期や用途については歴史的な議論が続いています。
状態によって価値が大きく変わりますが、割安な物なら3~5万円程度で購入できます。
- 形状:円形で中央に四角い穴が開いた孔方銭(こうほうせん)型。
- 材質:主に銅や青銅が使われており、少量の金や銀を含むものもあったとされています。
- 刻印:表面に「富本」の文字があり、裏面は無地のものが多いです。
- 製法:鋳造によるもの。
- 用途の議論:富本銭が広く流通する貨幣として使われたかどうかは不明です。一部では貨幣というよりも、儀式や祭祀に用いられたり、権威を象徴するものだった可能性が指摘されています。
- 意義:富本銭の存在は、7世紀末には日本が貨幣の鋳造技術を持ち、国家運営に貨幣制度を取り入れようとしたことを示しています。
708年
中国の唐の貨幣制度を模倣して「和同開珎」が作られましたが、日本国内での貨幣流通の浸透には時間がかかり、当初はあまり普及しませんでした。
その後、「万年通宝」や「隆平永宝」などの貨幣が続けて発行されましたが、物々交換が依然として主流でした。
- 材質:主に銅で作られており、一部には銀貨も存在しました。
- 形状:円形で中央に四角い穴が開いた「孔方銭(こうほうせん)」の形状をしています。
- 刻印:表面に「和同開珎」と刻まれており、裏面には何も彫られていないシンプルなデザインです。
- 「和同」:元号「和銅」を由来とし、「和銅」は日本で銅が発見されたことを記念して改元された元号です。
- 「開珎」:開始・開発を意味し、貨幣が新たな経済の基盤として用いられることを象徴しています。
人気の高い古銭で、その後は皇朝十二銭と呼ばれる12種類の硬貨が作られますが、それ以降は日本で貨幣を製造しない時代が続きます。
和同開珎の価値は一般的なもので1~5万円。
文字に跳ねがある稀少なデザインで状態が良いと100万円の値が付くこともあります。
1587年頃
安土桃山時代、豊臣秀吉が「天正大判」をはじめとした小判を作り始める。
戦国時代から安土桃山時代にかけて、日本国内の通貨は一元化されておらず、中国から輸入された永楽通宝などの銭貨や日本国内で鋳造された地方銭が流通していました。
- 純度の高い金で作られ、重さは約165グラム。
- 表面には「天正」の文字が刻まれている。
- 手工芸的な鋳造で、独自の美しさがあります。
- 豊臣秀吉は貨幣を統一し、金貨を鋳造することで権力基盤を固めるとともに、国内の商業や流通を促進しようとしました。
- 天正大判はその象徴であり、大判の制度を導入した初期の例とされています。
- 実際には通貨としてよりも、贈答品や権威の象徴としての役割が強かったとされています。
「天正菱大判」「天正長大判」「大仏大判」など、当時の小判はいずれも発行枚数が少なく非常に稀少で、価格は1枚100万円が下限です。
状態によっては1億円近い値段が付くこともあります。
1636年
「寛永通宝」江戸時代初期に発行された貨幣で、日本史上最も長期間にわたって流通した銭貨です。
発行は1624年(寛永元年)に始まり、全国共通の貨幣で、その後も江戸時代を通じて鋳造され続けました。
当時の古銭は安いもので1万円ほど、状態が良ければ30万円以上です。
- 材質:主に銅で作られていましたが、一部には鉄や鉄銭も存在します。
- 形状:円形で中央に四角い穴が開いた「孔方銭(こうほうせん)」の形式。表面には「寛永通寶(かんえいつうほう)」と刻まれています。裏面には鋳造地を示す特徴がある場合もあります。
- サイズ:初期の銭はやや大型(直径25~27mm)で重さもあり、後期になるとサイズや質が変化していきました。
- 初期銭(大銭)
- 通常銭(小銭)
- 鉄銭
- 地域ごとの特徴銭
寛永初年から発行され、銅の含有量が多く、しっかりした作り。
重量が重く、直径が大きい。
発行が進むにつれ、銭の大きさや重さが縮小。
銅の品質も時代が下るにつれ低下しました。
銅の不足時に発行された鉄製の銭。
鋳造地が増えたことで、各地の銭に特徴的なデザインや書体が見られます。
1871年
1871年(明治4年)は、日本の貨幣制度において大きな転換点となった年です。
この年、日本政府は新貨条例を制定し、西洋式の近代的な貨幣制度を導入しました。
これにより、それまでの江戸時代の貨幣(小判や文銭など)から、円・銭・厘を基本単位とする新しい貨幣制度に移行しました。
- 明治維新後、日本政府は貨幣制度の近代化を急いでいました。
- 江戸時代には金貨(小判)、銀貨(丁銀)、銭貨(銅貨)が混在し、地域ごとに異なる通貨が流通していたため、統一的な貨幣制度が必要とされました。
- 新貨条例の導入により、統一された近代的な貨幣制度が実現しました。
1932年
1932年(昭和7年)は、日本の貨幣制度にとって重要な時期でした。
この時代は昭和恐慌の影響が薄れつつあり、満洲事変(1931年)の進行などで日本経済や財政が戦時体制に向かいつつあった時期に該当します。
従来の金や銀など貨幣に使われる素材の種類と重さで価値が決まる制度から、発行元が決めた価格で流通する管理通貨制に移行しました。
また、紙幣の流通が拡大し、国立銀行券や日本銀行券が広く使用されるようになりました。
その後は東京オリンピック記念硬貨や天皇陛下即位記念硬貨など、幅広い種類の貨幣が造られていきます。
古銭売買の歴史
古銭の歴史に明確なデータはありませんが、コレクションとして古い貨幣を集めるようになったキッカケは1932年の管理通貨制への移行です。
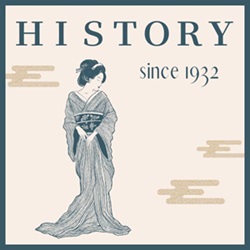
以前まで金や銀などの資産性が高い素材で造られていたものが、日本銀行の発行するアルミや紙製の貨幣に変更されたものの、当初は安全性が高い金で出来た昔の貨幣を好む方が多かったようです。
現代でも資産運用やリスク回避として金に投資する人が多く見られますよね。
当初は資産の確保を目的にしていたものが、時代の変化とともに希少性を評価されるようになり、1900年代に入ってからが広がっていきます。
1964年には日本で初めての記念硬貨が造られたように、貨幣は実用性だけではなく記念や希少性のあるツールとして普及するようになりました。
